オシレーター系チャートの代表格で
RSI=Relative Strength Indexの略で相対指数といわれていますが、
簡単に言って一定期間における値動きの強弱や売られすぎ・買われすぎを知らせる指標です。
オシレーター系チャートとは?
オシレーター系チャートとは、
一般的に「売られすぎ」「買われすぎ」を判断するのに使われる指標で、
急激な変化は修正されるはずという観点から、逆張りに最適な指標として参照されています。
RSIとは?
尚、RSIとは、為替レートの変動幅全体に対する”上げ幅”の割合を表した指数のことです。
RSIは、過去一定期間のレートの上げ幅の合計が
上げ下げ全変動幅の合計と比較して
どれぐらいの割合だったのかをパーセントで算出した数値で、
変動幅の基本的な計算は終値の差分で、日足であれば前日終値と当日終値の差分となります。
そして、その値を元に
「買われすぎ」「売られすぎ」の判断材料として使われるのがこの指標になります。

(参考:HYPER SBI)
トレンド相場の継続中にも上げ相場の天井を把握するのも重要で
RSIはその決済時やエントリータイミングを計るのに有効なのです。
チャートの読み取り方

~100%の値で表現され、
数字が100に近づくほど買いの勢いが強い、買われすぎを表し、
数字が小さいほど売りの勢いが強い、売られすぎを表します。
基本、RSIが70%以上で買われすぎ、30%以下で売られすぎという判断をします。
50%が真ん中なのでフラットな状態になりますが、
上昇トレンドでは、この50%以上の状態で推移することが多く、
下げ相場では逆に50%以下の状態で推移することが多くなります。
上記のように30%、50%、70%がRSIの重要な数値となりますので
割とシンプルでわかり易いといえるでしょう。
しかしながら、気をつけなければいけないのは、
30%や70%を超えたところで張り付いてしまったり、
意外と強いトレンドには弱くて、
RSIのシグナルが機能しなくなるときもあるので気をつけましょう。

RSIでは買われすぎと売られすぎを見極めることが可能で
逆張りのチャンスを探すときに有効な指標ですが、
現実的には単純にRSIが30%や70%をつけたからといって、
単純に逆張りエントリーをするという形だけだと、
必ずしもよい結果が出るとはいえません。
というのは、RSIの張り付きという弱点が出てしまうからです。
この張り付きによるダマシを回避するために
どういった条件を追加していくのか、というのが
RSIを使った取引におけるポイントになってきます。
方法としては、
RSIが30%や70%を超えたタイミングでエントリーするのではなく、
超えてから反転するのを確認するまで待つと、
張り付きの可能性は低くなり、賢明といえるでしょう。
もしくは、反転してから
30%や70%のラインを割り込んだタイミングまで待ってエントリーするという方法です。
ダイバージェンスのケース

RSIは、過去一定期間のレートの上げ幅の合計が、
上げ下げ全変動幅の合計と比較して
どれぐらいの割合だったのかをパーセントで算出した数値で
変動幅の基本的な計算は終値の差分で、
日足であれば前日終値と当日終値の差分となります。
そして、その値を元に
「買われすぎ」「売られすぎ」の判断材料として使われるのがこの指標になります。
ダイバージェンストは、
トレンドが上昇トレンドの場合において綺麗な上昇を見せているときに
このRSIが30くらいまで下落している、
いわば逆行のシグナルが出ているということです。





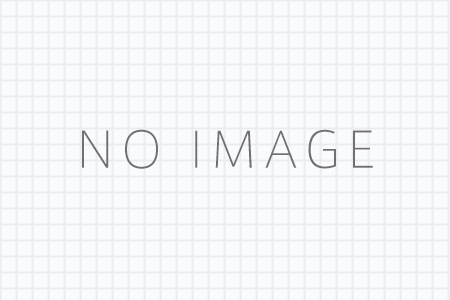


















コメントを残す